債権回収方法を分かりやすく解説しています。
債権が回収できないときに行う行動は以下の通りです。
- いつまでも待つ(5年で時効)
- 回収作業を行う(催促・内容証明・督促・催告・仮差押え)
- 債権回収代行業者に依頼する
- 裁判を行う
- 債権を売却する
- 諦める
さまざまな回収方法があるのですが、「自分で回収を行う」のか、それとも「専門家や代理人に依頼するのか」の2つの選択肢に分かれます。
またその前に、債権が回収できない可能性を見越し事前に取れる対応策もあります。
- 事前に売掛保証に加入しておく
- 債権譲渡のために手数料を上乗せ
債権回収の難易度にもよりますが、専門家や代行業者に依頼してしまったほうが回収できる可能性も高いですし、何よりも楽です。
目次
債権回収業務を自社で行うか 代理人に依頼するか
債権回収を行う方法としてまず「自社で行う」「代理人に依頼する」の2択となります。
回収作業は時間や労力がかかるものです。はじめのうちは自社で行い、回収できないようであれば代理人に依頼するのもよいでしょう。
よくある債権回収方法
未回収の債権がある場合に取れる行動は以下の通りです。
- いつまでも待つ(5年で時効)
- 回収作業を行う(催促・内容証明・督促・催告・仮差押え)
- 債権回収代行業者に依頼する
- 裁判を行う
- 債権を売却する
- 諦める
交渉での解決が一番簡単
話し合い(交渉)での解決が一番簡単です。
それ以外の方法を利用する場合、どうしても相手との間に少なからず亀裂が入ることとなります。
そのため売掛金を見払い状態にされてしまったら、まずはじめに話し合いをしてみてはいかがでしょう。もしそれで上手くいかないようであれば法的手段を検討してみるとよいかもしれません。
法的手段(督促・催告) 簡易裁判所を利用
簡易裁判所を利用し債務者である取引先に対し督促や催告といった手段を取ることができます。
法的書類を送付するだけでも支払いに応じる場合もあります。なぜなら裁判所を通しているため法的強制力を持っているからです。
これらは代理人に依頼せずとも行うことが可能です。しかしコスト(時間と手間)がかかることを考えると代理人に依頼するのもよいかと思います。
また代理人に依頼しているという事実がわかるだけでも、支払いを行う可能性もあります。
少額訴訟・通称訴訟・支払督促
法的手段として少額訴訟、通称訴訟、支払督促といった手段を利用することが可能です。
裁判所を利用するということもあり債務者からすると、債権者の本気さを伝えることができます。さらに無視をすることができなくなります。
この辺りの方法を利用するとなると、弁護士に相談したほうがよいことでしょう。
債権譲渡でストレスを失くす
債権を譲渡することで問題解決する方法もあります。
売掛債権は売掛金を債務者から受け取る権利です。その権利自体を第三者に譲渡(売却)してしまうのです。
第三者とは民間の債権回収会社であったりファクタリング会社となります。手数料は取れますが売却益が入ってくることになります。償還請求権ナシの契約であれば、将来的に問題が発生しても責任を負う必要はなくなります。
参照 償還請求権とは
不良債権は買い手がつきにくい
回収困難な債権(不良債権)は買い手がつきにくいです。債権を買い取った側が損をしてしまうためです。
そのためいくつかの業者に声をかけてみて、もしダメであれば回収業務を行うしかなくなるでしょう。
売掛債権のサービサーとは、「法務省から認可を受けている売掛金を回収する民間業者」のことです。
以前までは、売掛債権の回収代行業務は弁護士しか扱えない業務でした。しかしその権限を、ある一定の条件を満たしている民間業者でも扱えるようにしたのが「サービサー法」という制度です。
自分自身で売掛金を回収できない場合には、弁護士や回収代行業者に回収を依頼した方が売掛金を回収できる確率が高くなります。

自社で回収するか、それとも代理人に依頼するのかの2つとなるだろう。
債権の金額によってどちらを選ぶのかを考えてみるとよい。
包括的に考え代理人に依頼してしまったほうがよいかと思う。
債権金額が少額なら債権回収代行の利用は疑問
債権金額が少額である場合には、債権回収代行に依頼するのは疑問です。債権譲渡するのとあまり変わらない気がします。
なぜなら手数料が代行会社へ依頼するのも、債権譲渡するのもあまり大きな差がないためです。
債権回収会社の手数料は意外と高額
たとえば弁護士に債権回収業務を依頼したとします。
一般的には「着手金と成功報酬」が必要となります。
- 着手金・・・10万円~30万円
- 成功報酬・・・回収額の20%~30%
- 実費・・・弁護士の日当、交通費、内容証明郵便料、公正証書作成費用など
着手金が安くて10万円、成功報酬が安くて20%のため50万円×20%=10万円、その他必要となる費用としておおよそ10万円としましょう。
すると、50万円の債権を回収するために必要となる費用が30万円となってしまいます。手元には20万円しか入ってこないことになります。
これは安く見積もった場合の話です。場合によっては手元にほとんど帰ってこないケースもあることでしょう。
債権譲渡してしまったほうが手元に残る
債権金額にもよりますが、たとえば50万円であれば譲渡してしまったほうが手元に残るお金は多くなるかもしれません。
ファクタリング会社は債権の買取を行っていますが、債権金額の20%前後の手数料が必要となります。つまり10万円ということになり、40万円は手元に戻ってくるということになります。
ただしですが、ファクタリング会社は不良債権は敬遠します。そのためもし取り扱ってくれたらファクタリングを利用した方がよいかもしれません。

意外と弁護士費用は高くつく。数千万円や数億円といった高額な債権であれば弁護士の方が費用が安くなる傾向にある。
「自社で回収」 債権回収会社の手数料が心配なら自社で回収

自社で債権回収業務を行うことがはじめの第一歩でしょう。
たとえば以下のような回収方法を利用することができます。
- いつまでも待つ(5年で時効)
- 回収作業を行う(催促・内容証明・督促・催告・仮差押え)
- 債権回収代行業者に依頼する
- 裁判を行う
- 債権を売却する
話し合いによる解決がスムーズ 時間や手間がかかる場合も
一番よいのは話し合いによる解決です。
しかし話し合いに応じてくれないケースもあります。そうなってしまった場合には、さまざまな制度を利用することができます。
話し合いが上手くいかない場合、次に考えられるのは「内容証明を自分で作成して送る」といった手段です。
少し手間にはなりますが、自分で作成して送ることもできるのです。
参照 内容証明郵便での売掛金回収は有効な方法!内容証明には決まった文章形式がある
内容証明郵便は債権回収の第1歩 相手方にプレッシャーを!
内容証明郵便は債権回収の有効な方法の1つです。
取引先に本気度を伝えることができ、少なからずプレッシャーを与えることがができます。
またその後に裁判となった場合でも証拠となる得る書類となります。
内容証明郵便にかかる費用
内容証明郵便は次の費用が必要となります。
- 基本料金 82円
- 一枚 430円 以後1枚ごとに260円
- 書留料金 430円
- 配達証明 310円
例えば文書が2枚入った定型内の配達証明付き内容証明郵便を送る場合、
82円+430円+260円+430円+310円=1,512円
がかかります。
弁護士や債権回収会社に依頼するよりも格段に安いコストで済みます。
ただしなのですが、内容証明を出す際には郵便局員のチェックが入ります。そのチェックにパスしなければ送ることができないのですが、内容証明の書き方には細かなルールが数多くあり、少しでも間違えてしまうと送れなくなってしまうのです。
ちなみに私も内容証明を1度作成したことがありますが、郵便局と事務所を3度往復した経験があります。郵便局員のチェックは1回当たり約1時間前後かかりました。正直かなり手間でした。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便の文面例です。
令和〇年〇月〇日 東京都新宿区北新宿〇ー〇ー〇 株式会社 A 〇〇 〇〇殿 催告書 弊社は、貴社との平成〇年〇月〇日に 締結した売買契約により、 代金〇〇万円で貴社へ商品〇〇を売り渡しました。 しかしながら、繰り返しの電話による催促に関わらず、 現在まで代金〇〇万円の支払いを受けておりません。 令和〇年〇月〇日までに、 上記〇〇万円を下記口座にて支払うよう催告いたします。 上記の期日までに支払いいただけない場合、 法的措置を取らせていただきます。 記 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇 口座名義人:〇〇 〇〇 住所:東京都港区新橋〇ー〇ー〇 株式会社 B 代表:〇〇 〇〇 印
取引先企業との間で弁済期日を決めていなかった場合は、催告書に弁済期日を明記します。既に弁済期日を決めており、その期日を過ぎているときは早急に支払いに応じるよう促します。
催告書に明記されている支払いに応じなかったときは、法的手段に訴えることも記載しておきましょう。
内容証明郵便の決まり
内容証明郵便の文章に正確な決まりはありませんが、文字数と行数が決められています。
- 横書き文書:1行あたり13文字以内、1枚40行以内、または1行あたり26文字以内、1枚20行以内
- 縦書き文書:1行あたり20文字以内、1枚26行以内
用紙サイズに指定はありませんが、郵送用、控え、郵便局用に3通同じ文書を用意します。この文書3通はサイズを揃えます。文書が2枚以上にわたる場合は、綴じ目に契印を押しましょう。
郵便局の担当職員が中の文書を確認するので、封をしないで郵便局に持っていくようにしてください。
内容証明郵便を送った後の対応
内容証明郵便を送っただけでは債権回収ができません。相手先企業からの支払いに応じると連絡があった場合は直接交渉を行ない、返済期日や返済方法、期日に遅れた場合の対応などを決めてください。
交渉内容はすべて「公正証書」にまとめておきましょう。公正証書は内容証明よりも法的拘束力が強い証拠文書です。
交渉で決めた期日に支払わないなど、公正証書の内容に反故があった場合、その段階で諦めるのか、その先に進むのかを判断することになります。諦めたらその段階で終了。進むのであれば訴訟ということになります。
公正証書 証拠力の高い資料
公正証書を作成するといった方法もあります。
その場合には公証役場に行き公証人に作成してもらうことになります。公正証書は証拠として価値が高くなります。
支払い督促 簡易裁判所の制度
支払い督促の制度を利用し手続きを行うことで、簡易裁判所が支払いの命令を出してくれます。場合によっては仮差押えや強制執行というものもあります。
仮差押え 財産を抑える
仮差押えをすることで、相手が財産を抑えることができます。その後の強制執行で回収することが可能となります。
民事調停・少額訴訟・通常訴訟
民事調停・少額訴訟・通常訴訟といった方法もあります。
裁判や調停で当事者の合意で解決することができれば、和解調書や調停調書が作成されることになります。
ただしここまで来ると非常に手間と時間がかかります。そのため専門家や代理人に相談したほうがよいでしょう。
「代行業者や専門家に依頼」 弁護士・司法書士・売掛金回収代行業者

売掛金回収は弁護士・司法書士・売掛金回収代行業者などが行ってくれます。
売掛金回収代行業者とは、法務省から認可を受けた上で売掛債権回収代行を行なっている株式会社のことです。代行業者は弁護士法の特例として制定された「サービサー法」という特別措置法が施行されたことで誕生した業種であり「サービサー」と呼ばれています。
弁護士に債権回収を依頼をすることもできる 元々は弁護士の業務だった
債権の回収代行業務は弁護士や司法書士でも取り扱っています。
そもそもなのですが、元々は弁護士しか債権回収業務を許可されていませんでした。
しかし、バブル崩壊後に多くの売掛金や手形が不良債権化し、既存の弁護士だけでは債権回収業務代行に手が回らなくなってしまったのです。そこで日本政府は不良債権の効率的な処理をするため、1998年に「債権管理回収業に関する特別措置法:サービサー法」が公布され、弁護士以外の民間企業も債権回収業務を行えるようなったというわけです。
弁護士に債権回収を依頼をした場合でも、その他の民間業者と同じように依頼手数料は発生します。
2004年4月までは債権回収手数料は「弁護士法」によって上限額が定められていました。しかし弁護士法が改正されてからは、弁護士報酬の上限や下限を決めている規定がなくなったため、依頼する弁護士によって手数料が大きく異なってきます。
弁護士に回収依頼をする場合の手数料
一般的な話ですが、弁護士に何か仕事を依頼する際には、はじめに相談料が必要となります。30分5,000円~1万円など、時間によって相談料がかかるのです。弁護士事務所によっては「初回相談は無料」というところもあるため、回収コストを低く抑えたいのであれば、初回相談無料の弁護士事務所に相談してみるのもよいでしょう。
実際に依頼する場合、はじめに着手金が必要となります。いわば依頼するための契約料のようなものです。ただし、着手金は回収の成功と失敗に関わらず支払わなくてはなりません。一般的に弁護士への着手金は10万円~30万円が相場です。
債権額によって着手金の額を決めている弁護士事務所もあります。その場合の相場は次の通りです。
| 債権額 | 着手金の相場 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10万円程度または債権額の10%程度 |
| 100万円~500万円 | 15万円~30万円程度または債権額の8%程度 |
| 500万円~1,000万円 | 30万円~50万円程度または債権額の6%程度 |
| 1,000万円~3,000万円 | 50万円~100万円程度または債権額の4%程度 |
| 3,000万円以上 | 100万円以上または債権額の2~3%程度 |
債権の額が多いほど、着手金の割合が少なくなっている場合が多いです。一方で債権額が100万円以下の場合、手数料が10%を占めているため、負担が大きくなる可能性があります。
弁護士に依頼する場合、着手金以外に次のような費用が必要です。
- 成功報酬…回収額の20%~30%
- 実費…弁護士の日当、交通費、内容証明郵便料、公正証書作成費用など
債権回収を得意としている弁護士事務所の中には、最初の着手金は無料にしているところもあります。こうした弁護士事務所を選んで債権回収にかかる必要を抑えることも大切です。
注意すべきは、すべての弁護士が債権回収代行を得意にしているというわけでありません。弁護士と聞くと法律に関わることなら何でも依頼できそうに思えますが、そのようなことはないのです。もちろん法律的な手続きなどに関してはプロです。
しかし普段扱っている相談事は刑事事件や損害賠償など弁護士によって得意分野が異なることも事実です。債権回収経験が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。
回収業者に債権を委託・譲渡
債権回収業者に債権回収を代行してもらうことができます。その際には回収業務を委託するのか、それとも債権を譲渡するのかの選択になります。
どちらもコストがかかりますが、譲渡してしまったほうが気が楽になるという考え方もあります。
債権譲渡 売掛金を受け取る権利を渡すこと
債権譲渡とは、取引先から売掛金を受け取る権利を渡すということです。
A社がB社に商品を納品したとします。A社はB社に請求書を出すことになります。それに対しB社は支払いをすることになります。
これはA社がB社から商品代金を受け取る権利を持っているということです。
この権利自体を他社に渡すことが可能です。それが債権回収会社であったり、ファクタリング会社となります。
権利を渡すときには売却することになるため、売却益を得ることができます。
債権管理回収業に関する特別措置法が成立したきっかけ
債権管理回収業に関する特別措置法は別名「サービサー法」とも呼ばれています。サービサー法が成立したきっかけは、現在の不況の発端ともなった昭和後期から平成初期にかけて発生した「バブル崩壊」です。
バブル崩壊以降、手形の不渡りや売掛債権の不渡りなどで多くの企業が倒産しました。それまで大手と呼ばれていた大企業までもが倒産したことも社会問題になったのです。
法務省は、大量に発生した不良債権を処理しやすくするために、それまで弁護士にしか許可されていなかった債権回収業務を民間の会社にも手伝ってもらうために成立させたのが「サービサー法」なのです。
サービサー法は平成10年に成立しました。成立当初は100社程度の債権回収会社が認可を受けましたが、2019年12月11日の時点ではその数を減らして、計73社がサービサーとして債権回収業務を行なっています。
サービサーの認可基準の重要ポイント
サービサー法によって法務省から認可を受けるためには、厳しい審査が行なわれます。特に重要な基準があります。
- 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士がいる
弁護士であれば誰でも債権回収業務は行なえますが、弁護士にも得手不得手はあるものです。刑事事件を得意とする弁護士もいれば、債権回収を専門的に行なっている弁護士など扱う事件などに応じて経験値が異なります。
サービサーの場合は「常務に従事する取締役」として弁護士が任命されていることが条件です。理屈上は常勤している必要はありませんが、常に回収代行会社と連絡が取れ、担当している回収代行業務のすべてを把握していれば認可を受けられます。
誰に依頼してもよいということではない
簡単な回収業務であれば、実務経験などが無くても回収は可能かもしれません。
しかし回収業務が複雑になった場合には、交渉力や訴訟が起こったときの対応力などが求められます。取引先も弁護士で対抗した場合には弁護士の実力次第では訴訟で負けてしまう場合もあります。
訴訟で負けると債権が回収できなくなるばかりではなく、訴訟を起こしたことなどによる損害賠償や名誉棄損で逆に訴えられるケースもあります。
そのため実績豊富な専門家や回収業者に依頼したほうがよいでしょう。
法律事務所(弁護士)や司法書士が債権回収だった
以前までは、債権回収を代行するのは弁護士(法律事務所)でした。
または債権金額が140万円以下であれば認定司法書士といった限られた士業しかできない業務でした。
現在では民間業者も債権回収業を行うことができます。
債権にも多くの種類がある
債権回収代行業者が回収できる債権は以下の通りです。
- 金融機関等が有する貸付債権
- リース・クレジット債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
- 保証契約に基づく債権
- その他政令で定める債権
未収金も回収代行を依頼することができる
売掛金の回収を代行する会社があるというお話をしてきましたが、売掛金と似た性質を持つ「未収金」の回収に関しても代行してくれる会社があります。
参照 未収金とは
基本的に回収の仕方は売掛金と同じです。
- 電話での催促
- 内容証明郵便
- 支払い督促
- 訴訟・裁判
売掛金と未収金は性質は異なりますが、取引先から支払われていない受け取る権利のある売り上げです。権利がある以上は必ず回収しなければなりません。回収できないと結果的に自社が苦しむこととなります。
サービサーの利用手順

サービサーを利用する場合の利用手順を見ていきましょう。サービサーには3つの種類があります。
- 専門企業
- 金融機関の子会社・グループ会社
- 弁護士事務所の子会社・グループ会社
どのサービサーも申込手順は一緒ですが、金融機関や弁護士事務所の子会社やグループ会社は、窓口が銀行や弁護士事務所になる場合もあります。
弁護士事務所の場合は相談料が発生しますし、銀行窓口の場合はサービサーとのやり取りがあるため、申し込むまでに時間がかかる場合があります。

基本的な手順は次の通りです。
- 問い合わせ
- 債権の種類や状況のヒアリング
- 見積もり
- 機密情報や個人情報に関する覚書の差入れ・見積の提出
- 承諾と受諾基本契約の締結
- 債権情報の提出
- 債権回収業務の実施と業務遂行状況の報告
- 受託料の清算
売掛債権が回収できなくても受託料(依頼料)は発生します。倒産などで回収不可能になってしまうと、依頼料分を損してしまう可能性もあります。
回収手数料はピンキリ
債権回収会社は非常に便利な会社ですが、依頼するためには手数料が必要となります。
手数料は回収業者や回収方法によって異なります。以下がおおよその手数料相場です。
| 内容証明郵便 | 1万円~5万円程度 |
|---|---|
| 支払い督促 | 3万円~20万円程度 |
| 強制執行 | 5万円~20万円程度 |
| 民事調停・交渉 | 10万円~20万円程度 |
| 訴訟 | 10万円~30万円程度 |
内容証明郵便だけで相手先が支払いをしてくれればよいのですが、意外と全く反応しれくれないものです。そのような場合、訴訟にまで発展させることも可能です。回収業務として訴訟にまで発展すると、表に記載されているように10万円~30万円、場合によってはそれ以上の手数料が発生する可能性が出てきます。
売掛金の金額にもよりますが、売掛金額よりも回収するコストの方が高くなってしまうことも・・・。
あくまでも一般論ですが、売掛金総額が100万円を下回る場合には、債権回収会社を利用せずに自分で対処した方が良いという考え方もあります。自分では対処しきれない場合や、単純に売掛金を支払わない取引先に気分を害して収まりがつかない場合には、債権回収会社に依頼して毅然とした対応をすることも検討すべきでしょう。

注意すべき点は、もし回収できなかったらどうなるのか?ということを聞いておいた方が良いだろう。
サービサーは不良債権の買取りも行なっている
サービサーの中には債権回収業務の他に、不良債権の買取りサービスを行なっている所もあります。これ実は凄いことです。
不良債権とは、回収の難しい、支払期日の過ぎている売掛債権のことです。
債権の買い取りといえばファクタリングが挙げられますが、ファクタリングの場合には、確実に回収できる売掛債権しか買い取りません。つまり不良債権は買い取らないのです。
ところが債権回収代行業者の中には、回収の難しいとされる不良債権でも買取をしてくれるケースがあるのです。その場合には手数料を支払ってでも現金化することを検討した方が良いでしょう。
また最近では、サービサーがファクタリング業務を行っているケースもあります。はじめはファクタリングで申し込みをしておき、もし不渡りになるということであればサービサーの業務に切り替えるといったことができます。どちらにしても債権を持ち込む事業者にしてみれば、債権を売却することで資金調達ができることになります。

売掛金回収業者を使うメリットとデメリット 効率よく売掛金を回収できる


このように悩む事業者は少なくありません。売掛金が入って来ないことで取引先の心配をしている暇はありません。自分の会社の売り上げが入って来ない状態を解決することが先決です。
後日払いやツケ払い、掛払いなどの「代金を後日受け取る契約は信用取引といわれています。」。支払期日に支払ってもらえないということは、信用を裏切る行為として世間一般では捉えられているのです。
どんなに催促しても支払ってもらえる見込みがない場合には、売掛金の回収専門業者に依頼して代金の回収を行なうのも方法の1つです。
ただし1つだけ注意してください。売掛金回収業者の中には、許可を得ないで営業をしている業者がいるとされています。
悪質でない売掛金回収業者を選ぶには「法務省認可」があるのかが重要な判断基準です。法務省認可がない回収業者の場合は、悪質な業者の可能性があります。
取引先から支払ってもらえない売掛金を回収することは確かに大事です。しかし悪質な回収業者に回収業務を依頼することで、余計な支出をする羽目になるのだけは避けなくてはなりません。
参照 売掛金が回収不能になったときの対処法 売掛金問題を解決と防止するための5つの方法
3つのメリット 効率よく売掛金を回収できる
自分で売掛金を回収するのではなく、売掛金回収業者に代わりに回収作業を依頼するメリットは数多くあります。
とくに大きなメリットは次の3つです。
回収作業を依頼するためコストはかかりますが、それだけの価値はあることでしょう。ただし未回収の売掛金の金額と回収業者への依頼料のバランスは大事です。
売掛金回収に悩まず経営に集中できる
売掛金の回収がなかなかできないと、メンタル的にも資金的にもストレスになり、他の仕事にも支障が出てくる場合があります。
支払いをしてくれない取引先とのやり取りほど、無駄なものはありません。回収業務など、取引先が支払いの約束さえ守ってくれれば、必要のない業務なのです。「時は金なり」というように、その時間で新たな事業を展開する方が、よほど会社の将来のためになります。
本当にすべきことに集中するためにも、売掛金回収会社の利用して回収業務を代行してもらうことは「時は金なり」のためのメリットになるのです。


だからこそ、回収業者に依頼するという方法があるわけだ。
取引先が支払いに応じやすくなる
売掛金回収業者を利用することで、取引先に対して「法的な手続きも簡単に取れますよ」という意思表示ができます。
支払期日を過ぎても売掛金の支払いをしない取引先が相手の場合には、売掛金回収業者を利用することで、こちらの本気さも伝わりますし、後に裁判などの訴訟を起こす際にも有利となります。
回収業者は法務省から認可を受けることで営業しています。その認可を受けるためには、常勤の取締役に「弁護士」がいなければなりません。つまり回収業者の回収業務は法律にのっとったものとなるのです。
代金を支払わない取引先にとって「売掛金回収業者を利用すること」自体が見えない圧となって、取引先にのしかかります。取引先に悪意があって支払いを行なっていないのではあれば、裁判で負ける可能性は十分高くなります。
裁判に負ければ裁判所命令によって強制的に支払いをしなければなりませんし、裁判で発生する費用や時間もかかってしまいます。
よって自分に非がある分かっている取引先の場合は、こちらが回収業者に回収業務を依頼したことが分かった時点で、自分がどれだけ不利な状況にいるのかに気づき、渋々ながらも支払ってもらえる可能性が高くなるのです。
コンプライアンスを優先できる
自分で取引先に売掛金の催促を行なう場合、回収業務がストレスとなり、法的なボーダーラインを超えてしまう恐れもあります。確かに支払うべき代金を支払わない取引先に問題があるのですが、催促の仕方に問題があると相手から迷惑行為と判断されてしまうこともあります。
すると話は変わってきて、催促している側が不利な状況になってしまいかねません。場合によっては訴えられてしまいます。
売掛金回収業者は弁護士が回収業務を管理・監督しているため「コンプライアンスを優先した回収業務」ができます。
コンプライアンスとは法令を守ることです。つまり法律にのっとった回収方法で、取引先から代金を回収できるのです。これは非常に大きなポイントです。

どんなことをしてでも回収!相手の嫌がることをしてでも回収!

もしも裁判になったとき、少しでも有利に話を進めたいのであればな。
2つのデメリット コストと損失
一方で、売掛金回収業者に依頼することで発生するデメリットもあります。
- 回収コスト(依頼料)が発生する
- 想定外の損失をする可能性がある
回収コスト(依頼料)が発生する
売掛金回収業者を利用すると、どんな回収業務であっても依頼料が発生します。売掛金回収業者は、手数料や依頼料で利益を出しています。
もし回収業務がこじれてしまい、裁判などの法的回収業務が発生すると、費用が別に必要となるケースがあります。すると予定よりも回収コストの負担が大きくなる可能性が出てきます。
- 手数料
- 訴訟の場合は裁判所に納める費用
- 諸費用(交通費や日当、調査費など)
諸費用は書類を作成する際に発生する印紙代や交通費も含まれています。売掛金の金額と回収コストのバランスを考えないと、売掛金回収業者に依頼することで利益が大幅に減ってしまう可能性もあるのです。

予定外の損失をする可能性がある
売掛金の回収業務は自分で行うことができます。ただし回収業者に依頼したほうが手間がかからないという点ではメリットです。とはいえ、代理業者に依頼するということは依頼料がかかってくることも事実です。
たとえば内容証明は自分で作成することができます。作成したものを郵便局に持っていきチェックしてもらい郵送するだけです。この内容証明の作成を回収業者に依頼した場合には、数万円の依頼手数料が発生する可能性があります。裁判をしないと回収できない場合は、弁護士や売掛金回収業者に依頼すべきですが、それ以外の回収業務であれば、自分でやり方を調べて行なった方がコストが安く付くのです。



100万円以下の債権なら自分で行なう選択肢が有効!?
売掛金の回収に慣れていない経営者にとって、債権回収会社は非常に便利な存在です。取引先にとっては売掛金の回収を委託したというだけで相当なプレッシャーを与えられます。
しかし債権回収会社に支払う手数料もあなどれません。債権回収会社の手数料は会社や回収方法によって異なりますが、最も簡単な内容証明郵便だけでもかなりの額がかかるのです。債権額が100万円以下の場合は、自分で債権回収を行った方が回収コストを低く抑えられます。
参照 売掛金が回収不能になったときの対処法 売掛金問題を解決と防止するための5つの方法
回収代行の認可を受けるための10の基準

売掛金回収代行業者として営業するためには、法務省からの認可が必要です。法人の起業や個人事業主の営業届とは違い、代行業者として営業するために厳しい基準が設けられています。

参照 債権管理回収業のための申請・届出の手引(平成31年4月)
とくに重要なのが、次の3つです。
- 第4号:常務に従事する取締役のうちに、その職務を公正かつ的確に遂行できる知識と経験を有する弁護士がいる
- 第5号:暴力団員または暴力団でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配していない
- 第8号:債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有ている
それぞれで重要なポイントについて簡単に解説します。
第4号の「常務に従事する弁護士」とは、弁護士が売掛金回収代行業務全般を把握しており、なおかつ外部委託されていない弁護士が在籍しているということです。
第5号の「事業活動を支配していない」とは、請求をしてきた売掛金回収代行業者の社長やオーナー、株主や融資をしている会社に暴力団関係者がいないかということです。
第8号の「債権回収業を適正に遂行するに足りる人的構成」とは、請求を受けた回収代行業者の社員が、業務を適切に行なえているか、知識があるかという点になります。もし、回収業務を行なう社員や補助員が間違った債権回収業務を行なっている場合は、認可取り消し、もしくは認可を最初から受けていない業者の可能性があります。
法務大臣の許可を得た会社
債権回収代行業者は、法務大臣の許可を得た民間の会社となります。
認可を受けているかどうかは、法務省のホームページに掲載されている「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認することができます。
掲載されている情報は次の5つです。
- 営業許可年月
- 商号
- 代表者名
- 本店所在地
- 電話番号
請求された回収代行業者の社名(商号)や電話番号を確認して、もし一致していない場合は、認可済業者の名前を騙った詐欺業者の可能性が非常に高いです。
無認可業者はサービサー法違反で処罰される
無認可で債権回収業を行なっていると判明した場合、サービサー法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方の刑罰が課されます。要は犯罪として裁かれるのです。
無認可であることに加え、回収業務で恫喝や暴力などを行なった場合、さらに傷害罪なども加算されます。認可されている回収業者は合法的な回収業務しか行ないません。回収方法についておかしいな?と感じたら、すぐに消費者センターや弁護士、警察に相談しましょう。
認可外のサービサーは詐欺業者の可能性も
サービサーは、法務省の認可という強力な信頼の証を持っています。しかし「認可を受けている」と偽ってサービスを展開している業者も存在します。
そもそもですが、法務省から認可を受けている業者は、法務省のページに一覧で掲載されています。
たとえば、このページに記載されていない会社で法務省認可のサービサーと名乗っている場合には利用を避けた方がよいでしょう。また、実際にこのホームページに掲載されている業者であっても、その名前を無断で利用する悪質業者も中にはいるという話も聞きます。悪質業者に捕まらないためにも、法務省ホームページに掲載されている情報と、回収代行業者のホームぺージの情報が合致しているかを最低限確認しましょう。
- 営業許可年月日
- 商号
- 代表者名
- 本店所在地住所
- 電話番号
もし違っていることを発見して、その業者から「変更になった」といわれても信じてはいけません。変更があった場合は速やかに法務省へ届け出なければいけないためです。
サービサーを検索する場合は、法務省のホームページに記載されている情報を元にして調べることをオススメします。サービサーのホームページには「当社の名前を騙った詐欺事案」や「当社の職員の名前を騙った詐欺行為」といった注意書きをしている業者もあります。
つまり、法務省の認可というのは詐欺業者にとっては喉から手が出るほど欲しいモノなのです。人の弱みにつけこんだ悪質な詐欺業者ですから、必ずサービサーに債権回収代行を依頼する際には確認を行ないましょう。
認可済み債権回収会社を選ぶべき理由
手数料の安さだけで、債権回収会社を選ぶことはさけてください。認可されていない債権回収会社は、回収業務の一部しかできません。訴訟などは認可されている債権代行業者しか行えないのです。
最近では探偵事務所が債権回収業務を行なっている場合がありますが、その探偵事務所が法務省の認可を受けていない場合、取引先が夜逃げした場合の居所調査などしかできません。訴訟などには一切関与できないのです。回収業務の一部しか行なえないのに、高額な依頼料を求められるケースもあります。
ただでさえコストがかかる債権回収業務。さらに余計なコストがかからないように注意してください。
債権回収代行詐欺業者の手口

売掛金の回収代行業者は、法務省から認可を受けた民間会社しか営業ができません。
法務省からの認可を受けずに詐欺紛いの業務を行っている業者がいるとされています。手口として多いのは「架空債権の請求行為」と「認定外の業者が債権回収手数料を搾取する行為」です。
架空債権の請求行為とは?
法務省の注意喚起メッセージによると
実在する債権回収会社と類似の商号をかたり「債権移行につき確認事項が御座います。本日中に必ず御連絡ください。」と記載したショートメールが送付される事案が多数報告されています! 御注意ください。
このような文が表示されています。
参照 債権回収会社と類似の名前を語った業者による架空の債権の請求に御注意ください(法務省)
未払いの支払いや債権、借金がないのにも関わらず
「債権移行につき確認事項が御座います。」
というような文面で、架空債権の支払い請求をされているといった事案が、法務省や消費者センターに寄せられているとのことです。

要するに、本来は発生していない支払いを、まるであるかのように装って支払わせるということだ。
以前は個人に対しての詐欺行為が多かったが、最近では法人に対しても詐欺業者が接触してくることがあるようだ。

法人向けの詐欺業者であれば、請求書の照合などですぐに判明できますが、売掛金や買掛金の管理をきちんとしていない場合は、誤って支払ってしまうことがあるのです。
架空債権の請求行為を見抜く3つの方法
架空債権の請求行為を見抜く方法は全部で3つです。
正直確実で早いのは債権譲渡元に確認を取ることです。
ハガキなどの文書で請求された場合「債権譲渡を受けた」と記載されている
債権回収代行業者からハガキなどの文書で請求がされている場合、その文面を確認してください。
文面に「債権譲渡を受けた」と書かれていたら、債権譲渡通知が社内の関係機関に届いているかの確認をしましょう。
そもそもの話ですが、債権譲渡通知を行なわずに債権を第三者に渡すことはできません。通知も来ていないのに「債権譲渡」という言葉が書かれていたら怪しんでよいと思います。
具体的な明細がない
「商品代金分」などの記載はあるものの、商品名や商品番号など具体的な請求明細がない場合は架空請求の可能性が高いです。請求者はどんな場合であっても「利用明細」や「商品明細」(納品書など)を提示しなくてはなりません。請求明細の請求の根拠がなければ不正な請求になります。
法務省認可通達書など行政と関わりのあるような記述がある
法務省認可通達書や法務省認可特殊法人といった、行政と関わりのあるような記述がある場合、詐欺業者の可能性があります。行政では「通達書」のような文書は発行しません。

そもそも債権譲渡通知はなかなか受け取るものではない。だから初めて見た人はビックリしてしまうことだろう。
少しでも疑問を感じたのなら念のためにも関係各所へ相談したほうがよいだろう。
- 「債権譲渡を受けた」のような文章がある
- 請求内容を証明する具体的な商品名などが記載されていない
- 行政は通達書などは発行していない
- 目隠しシールのないハガキでの請求や督促
- 連絡先として多数の電話番号が並んでいる
- 請求書面で担当者の連絡先として携帯電話を指定
- 個人名義の口座を回収金の振込先に指定
架空債権の請求を受けた場合の対処方法
架空債権の請求を受けた場合の対処方法は1つ「無視すること」です。
お金を払えば解決するという考えはNGです。もし支払ってしまった場合、架空債権の請求内容を認めることにもなりかねません。
裁判を起こされた場合、支払いをしたという事実が不利に働いてしまう可能性もあるのです。請求している会社の電話番号などを保管しておき、法務省や警察などに通報しましょう。支払いや詐欺業者への連絡などは一切しないようにしてください。
- 無視する
- 文書などの証拠書類を保管しておく
- 警察などに通報する

なのでそもそもの話だが、資金調達や資金繰りを改善させ未払いの買掛金はすぐに支払うべきだろう。
「違法業者の債権回収行為」とは?
債権回収代行業者とは法務省から認可を受けた民間の回収代行会社です。取締役に常勤の弁護士免許保持者がいることなど、厳しい審査の上で認可を受けています。
しかし近年では、売掛金の回収不能による資金繰りの悪化で、多くの中小企業が倒産しています。そのため売掛金の回収業務を代行会社へ依頼しようという意識が高くなっています。
このような意識の変化につけこんで無認可の業者が、さも認可されていると偽って回収代行業務を行なっているのです。しかも、回収業務は本来の認定業者は絶対にやらない方法で取り立てを行ないます。たとえば、深夜の電話連絡や暴力や暴言による嫌がらせなどが挙げられます。

債権回収代行ができるのはあくまでも認定業者のみ
債権回収代行ができるのはあくまでも法務省の認可を受けた業者のみです。
ここでの回収代行業務とは「売掛金の回収を法的手続きを行なって行うこと」です。
この法的手続きには弁護士免許が必要です。または常勤の弁護士が取締役にいなければなりません。もし探偵事務所が売掛金回収代行を行なっているのであれば、常勤している弁護士がいるかどうかの確認をした方がよいでしょう。
探偵会社が売掛金回収業務に見せかけた詐欺行為を行なっている場合もあります。主に次のような手口があります。
- 依頼手数料を受取り、そのまま音信不通になってしまう
- 詐欺被害金の回収ができると偽り依頼料を搾取する
ではどうして探偵事務所が売掛金回収業務を行なうというような詐欺行為に手を染めるのでしょうか。
探偵業者は債権回収サポートであれば可能
探偵業者の専門分野は「事実調査」です。売掛先である会社が夜逃げをしてしまった場合、その会社の社長の所在地を探したり、他に資産を持っていないかなどの事実を調査したりするのは合法です。
しかし探偵業者が、認可もないのに売掛金の回収業務を行なうことはできません。もし回収業務を行なった場合は、探偵業者はもちろん、売掛金の回収を依頼した側も罪に問われる可能性があるのです。

債権回収代行業者を利用する側として気を付けたいこと

ここからは債権回収代行業者を利用する側として、気を付けたいことをお話ししていきます。
売掛金の回収業務を外部業者に依頼するのであれば、「弁護士」「司法書士」「代行業者」の3つに絞られます。
どこにお願いするにしても、費用や手続きの方法を事前に確認するしましょう。そして必ず相見積もりを取りましょう。
認可業者に依頼する場合は法務省ホームページで確認してから
認可業者のほとんどは専門のホームページを持っています。そこには業務内容の詳細が掲載されています。ここで注意してほしいのは、そのホームページの会社が本当に認可されている会社であるかどうかです。
類似業者や詐欺業者がホームページを作っている場合もあります。ホームページの情報を鵜呑みにするのではなく、正しい情報を元に業者選びを行ないましょう。
認可業者はこちらの法務省ホームページに記載されています。
ホームページ上の情報(代表者名や電話番号、住所など)をアクセスした対象の業者と合致しているか確認してから見積もりや相談を行なってください。
支払期日前の売掛金ならファクタリングで資金調達も検討しよう
売掛金の回収業者に依頼するタイミングは、代金の支払予定日が過ぎて、自分での回収が困難になった場合です。
もしまだ支払予定日が来ていないのであれば、リスク軽減という名目で売掛金を売却して最低限の利益を確保する方法もあります。
売掛金を売却する方法を「ファクタリング」といいます。ファクタリング会社に手数料を支払って売掛金を買い取ってもらう方法です。売掛金回収業務が必要となる前にファクタリングを行なっておくと、万が一売掛金の支払遅延が起こった場合に、その回収業務をすべてファクタリング会社に譲渡できるのです。
参照 ファクタリング
未回収の債権は必ず回収!

未回収の債権は何としてでも回収するようにしましょう。
それが自社の経営に大きく響くためです。そもそも気分の良いものではないですし。
方法としては自社で行うのか、それとも専門家や代行業者に依頼するのかの2つに大別されいます。
少し変わった方法としては債権自体を譲渡してしまうといった方法もあります。
債権回収時の注意点 ない袖は振れない
債権回収できるのも取引先に支払うお金や財産がある場合です。
未払いの期間が長くなればなるほど、相手方の経営状況が悪化する可能性がありますし、財産を処分されてしまうリスクが生まれてきます。
そのため、下請法の60日が過ぎるまでは待ったとしても、それ以降の支払いがない場合には、適切な行動を取ったほうがよいでしょう。

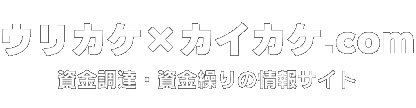







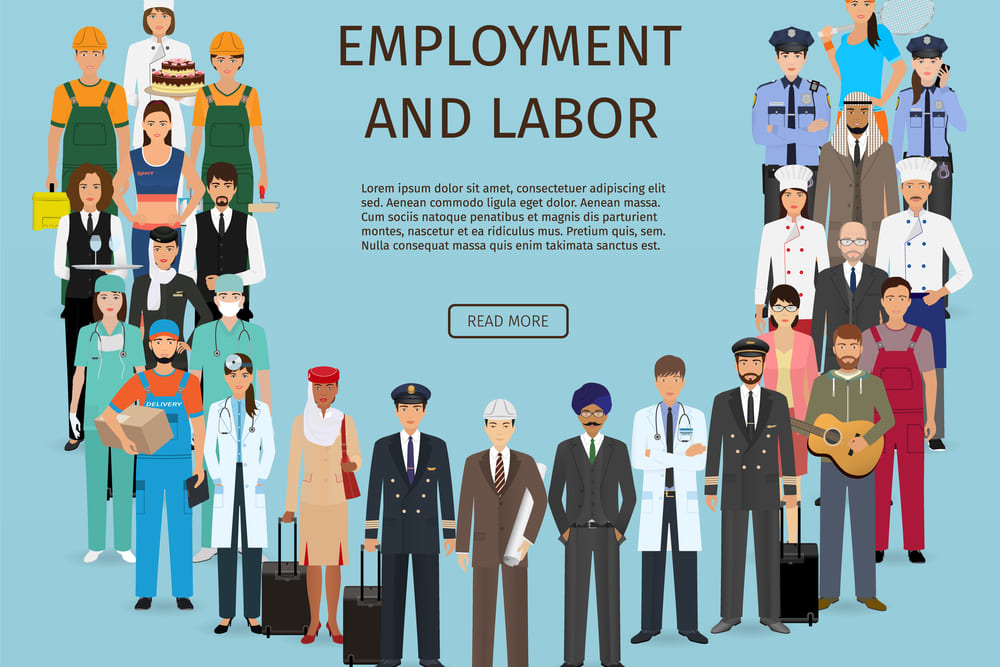
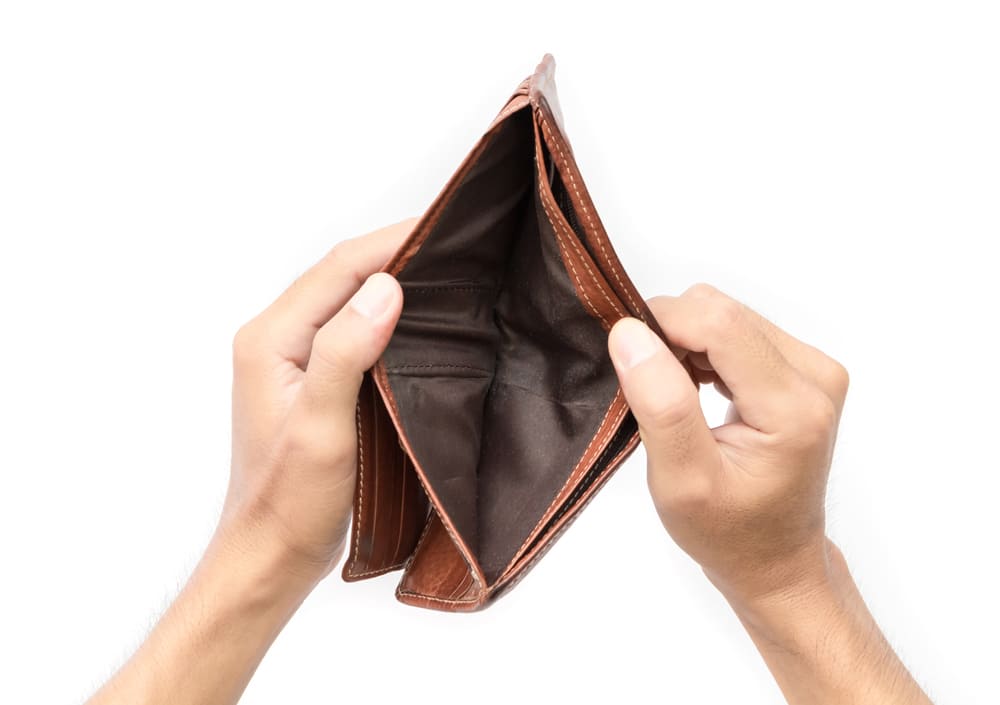




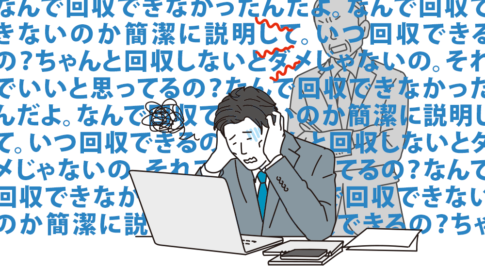
















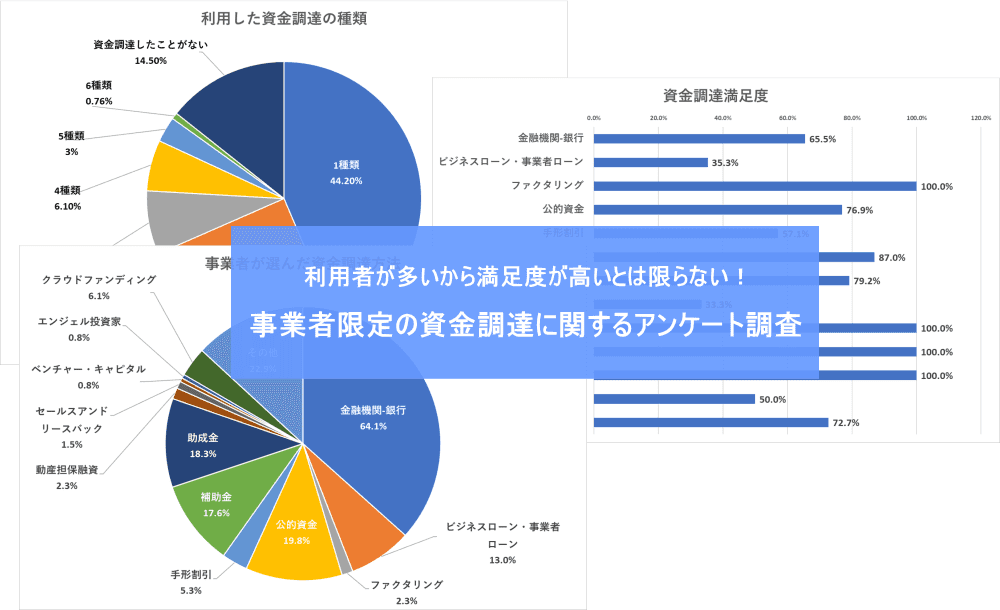


コメントを残す